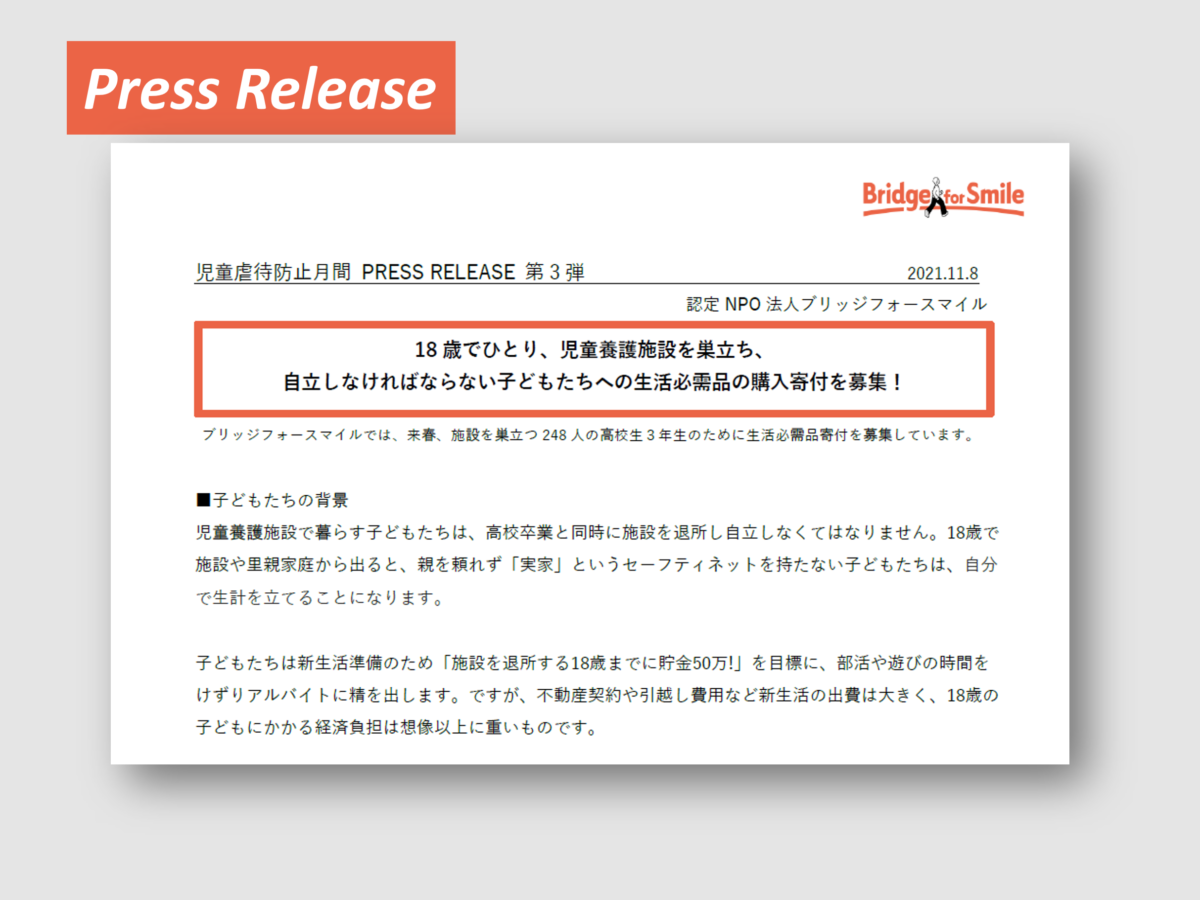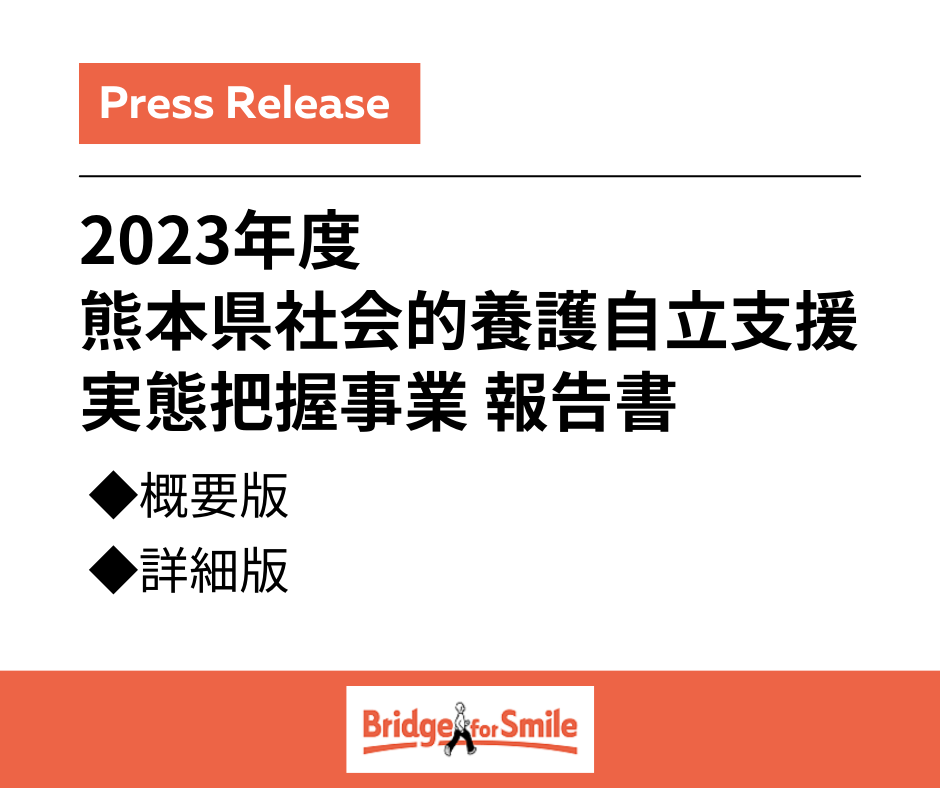
ニュース・活動報告
先日、子ども・若者支援担当のスタッフ矢森のコラム「厚生労働省が公表した実態調査によせて」が掲載されましたが、私も、調査つながりで、数字を見て思ったことを少し書きたいと思います。
4月に、児童養護施設や乳児院で生活する子どものうち外国にルーツのある子は全体の約3.8%いる、という朝日新聞の調査報道(*1)がありました。
みなさんはこれを聞いて、どんなことを考えますか?
私は二つのことが思い浮かびました。
一つは、意外と少ないという印象です。
児童虐待が起きてしまう原因の一つに養育者のストレスがあります。転勤などで職場や住まいが変わったことで、ストレスがたまってしまう、さらにそれを相談する相手がいないなどから、そのストレスのはけ口が子どもになってしまうこともあります。
外国で生活をしていて、文化や言葉の壁がある中、自国で生活するよりストレスがたまりやすい環境下では、児童虐待のリスクは高まるといってもいいかと思います。そのため、措置される子ももっと多いのではないかと思っていました。
最悪のことを考えるのであれば、保護者も子どもも言葉の壁などによってSOSを出せないため、措置まで繋がっていない可能性もあります。
逆にポジティブに考えるのであれば、日本にはない育児に関する価値観や独自のコミュニティがあることで、ストレスを上手くコントロールできている可能性もあるのかなと思いました。
もう一つは、最近知り合ったムスリム(*2)の方のことです。
私はその方にお会いするまで、イスラム教についてはそれほど詳しくありませんでしたが、その方からいろいろお話を聞くことで、イスラム教についてだけでなく、信仰を大切にする方の考え方の理解を深めることができました。
一方で、その方にお会いする前の元児童養護施設職員当時を振り返った時、ムスリムの子が入所して来たら、はたして適切な対応ができただろうかと考えると、難しいだろうなと思いました。
例えば食事一つをとっても、信仰を尊重したメニューにできるだろうか? 仮に本人は幼く、食事に関する決まり事を知らないが、両親は共にムスリムだった場合、どこまで食事に配慮するべきなのだろうか? などを考えた時、おそらく適切な対応はできなかったと思います。
そうして考えていくと、果たしてクリスチャンの場合の配慮はどんなことがあるだろうか、外国にルーツのある子の信仰だけ配慮するべきなのだろうか、そもそも信仰以外で配慮することは何があっただろうかなど、さまざまなことに考えが派生しました。
さて改めて、みなさんはどんなことを考えましたか?
*1 出典:「児童養護施設などに外国ルーツ637人 無国籍の子も」2021-04-17 朝日新聞デジタル
*2 イスラム教徒を意味するアラビア語

お互い迷惑をかけない社会じゃなくて、迷惑を気にしない人が増える社会になるといいなと思ってます。
-
2024.03.18広報・啓発活動【プレスリリース】 令和5年度 熊本県社会的養護自立支援実態把握事業に ブリッジフォースマイルが参画しました
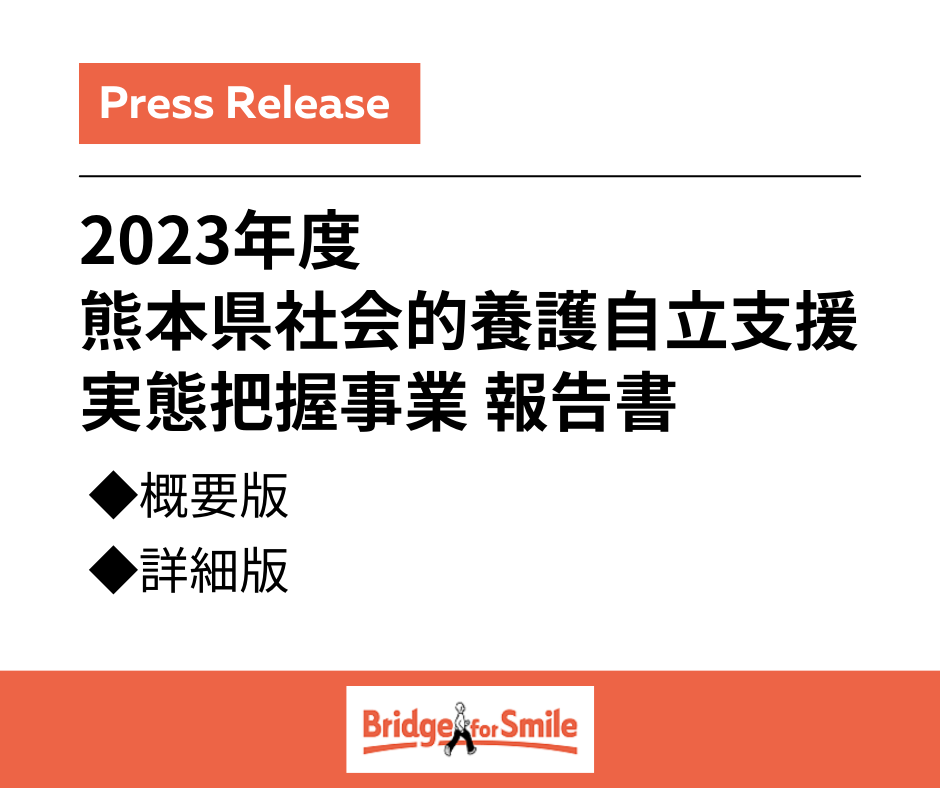
-
2024.02.19広報・啓発活動理想の巣立ち支援の実現に向けて ~緊急のご寄付のお願い

-
2021.11.08広報・啓発活動【プレスリリース】児童虐待防止推進月間・第3弾『生活必需品の購入寄付を募集!』