
ニュース・活動報告
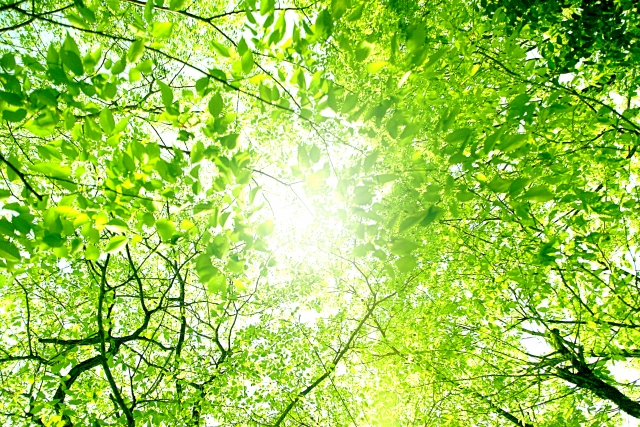
1947年に制定された児童福祉法により、児童養護施設は18歳までの子どもたちを支援することとされています。しかし高度経済成長期、子どもたちは働き手として金の卵と重宝され、義務教育を終えると当たり前のように施設を退所し就職していきました。
経済発展を遂げた日本で高校進学が一般的になると、1973年より施設でも高校進学が選択できるようになり、高校に進学する人は高校卒業まで施設に居られるようになりました。それから少しずつ高校進学率は上がり、いまでは96.3%の子どもたちが高校進学をしています(※)。
中卒で就労する場合は中学卒業と同時に、高校を中退する場合も、学校に行かないことは、つまり「 働く」と解釈され、退所を促されます。しかしながら、中卒者や高校中退者こそ自立が困難で、社会適応が難しい子どもたちといえます。
自立援助ホームという働きながら自立を目指すための小規模施設での支援が生まれたり、通信教育とフリースクールを組み合わせて施設でなんとかサポートを続けたりといった取り組みが進められてきました。
18歳に達した後も、児童養護施設での養育を20歳に達するまで延長できる「措置延長」は、児童福祉法第31条に定められていますが、判断をするのは児童相談所です。例えば、自立の準備が整っていない子どもに対して、施設職員が措置延長の必要を訴えても、児童相談所がダメと判断すれば施設職員は従わざるを得ません。
現状、簡単に措置延長を認めることができない事情があります。一時保護所には施設への入所待ちをしている子どもが多数いるからです。そのため、施設が定員いっぱいの状態になっている地域では、措置延長が認められないことが多くあります。平成29年のデータでは、高校卒業と同時に施設を退所する子どもは82.7%となっています(※)。
(事務局スタッフA)
※出典:社会的養育の推進に向けて(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課:平成31年1月)
-
2024.06.29広報・啓発活動社会的養護自立支援拠点事業がはじまりました

-
2024.07.08広報・啓発活動2023年度「年次報告書」ができました

-
2024.06.29広報・啓発活動コエールが、新しくなります! 【前半】スピーチができるまで


